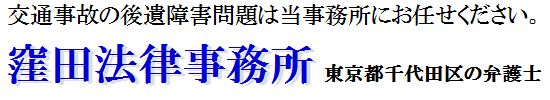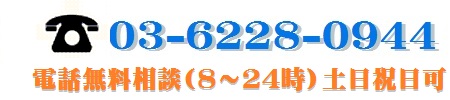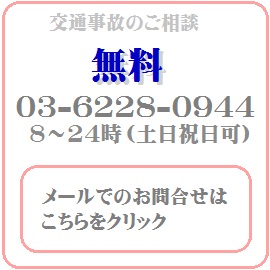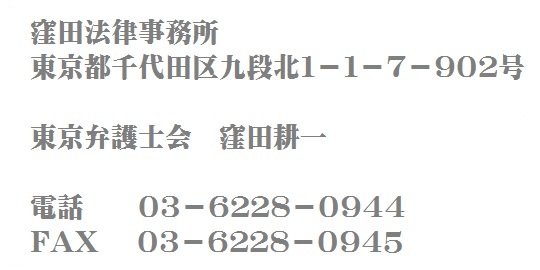耳の後遺障害等級(聴力障害)
聴力障害
耳の聴力障害は、両耳の場合と片耳で分けて規定がなされています。
両耳
| 等級 | 障害内容 |
|---|---|
| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
・「両耳の聴力を全く失ったもの」とは、両耳の平均純音 聴カレベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベ ルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
・「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、 1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上であり、かつ、 他耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
・「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。
・両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとの等級により併合の方法を用いて準用等級を定める取扱いは行いません。
片耳
| 等級 | 障害内容 |
|---|---|
| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
・「1耳の聴力を全く失ったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上のものをいいます。
・「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のものをいいます。
・「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は1耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。
・「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。
聴力障害の検査について
・聴力障害の等級は、純音による聴力レベル及び語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として判断されます。
・純音聴力レベルはオージオメーターという機器、明瞭度はスピーチオージオメーターという機器で測定します。
・障害等級認定のための聴力検査は、オージオメーターで日本聴覚医学会による聴覚検査法によります。
・純音聴力検査は日を変えて3回行います。
・純音聴力検査と検査の間隔は7日程度あければ足りることとされています。
・障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行うこととされています。2回目と3回目の測定値の平均純音聴カレベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を行い、 2回日以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴カレベル(差は10dB未満。)の平均により、障害認定がなされます。
・平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、次の式により求めます。
(A+2B+2C+D)÷6(6分法)
A=周波数500ヘルツの音に対する純音聴カレベル
B=周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
C=周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
D=周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル
・基本的には、純音聴力検査と語音聴力検査の結果をもとに判断されますが、追加的に被検者の意思によるコントロールが不可能な聴性脳幹反応(ABR) 、インピーダンスオージーメトリーという機器を使ったあぶみ骨筋反射(SR)という検査を補助的に求められることもあります。