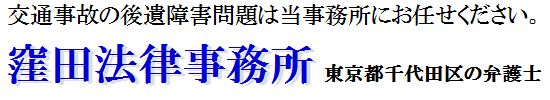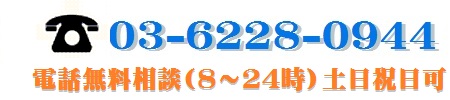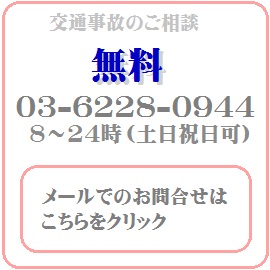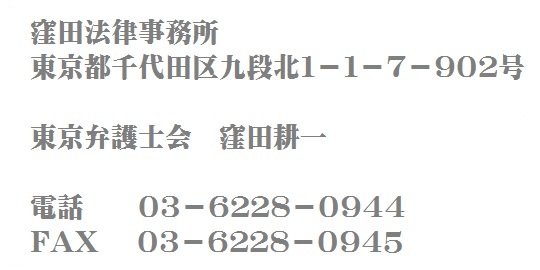労災における高次脳機能障害の後遺障害等級
まず、交通事故の場合になぜ、労災の等級を意識する必要があるかについてご説明します。
自賠責保険(損害保険料率算出機構)は、平成19年2月2日の報告書において、
「従前の考え方を用いて後遺障害等級を認定した後、労災保険で使用している「高次脳機能障害整理表」に当てはめて検証し、最終結論とすることが労災保険に準拠する自賠責保険としての妥当な認定方法と考える。」
としています。
ようは、自賠責保険の基準で後遺障害の等級を認定する場合に、労災保険の基準でも検証しながら結論を出すということです。
そのため、高次脳機能障害について、自賠責において適切な後遺障害の認定を受けるためには、労災の認定基準を意識しながら、被害者やご家族の方においてどのような後遺障害が残っているかを検討しておく必要があるのです。
実際上も、高次脳機能障害の等級は、介護の状況・仕事や日常生活への影響の度合いにより、等級が決定されるため労災保険の基準を意識しておく必要があります。
また、等級認定を受けるための「日常生活状況報告」を作成する場合にも、労災の基準を意識することで後遺障害による支障が整理しやすくなります。
労災における高次脳機能障害の認定は、まず、介護が必要となるか否かで大きく分かれた後、介護まで必要とならない場合には、①意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)②問題解決能力(理解力、判断力等)③作業負荷に対する持続力・持久力④社会行動能力(協調性等)について、下の高次脳機能障害整理表をもとにランク付けを行い、高次脳機能障害等級別認定基準にあてはめます。
労災保険における高次脳機能障害等級別認定基準
| 1級 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等常時介護を要するもの (b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの |
|---|---|
| 2級 | 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」 以下の(a)、(b)または(c)が該当する。 (a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等随時介護を要するもの (b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時他人による監視を必要とするもの (c) 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの |
| 3級 | 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの (b) 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの |
| 5級 | 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力が大部分失われているもの (b) 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの |
| 7級 | 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」 以下の(a)または(b)が該当する。 (a) 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの (b) 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの |
| 9級 | 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 高次脳機能障害のため、4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。 |
| 12級 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当する。 |
| 14級 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」 MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷があることが 医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失 が認められるものが該当する。 |